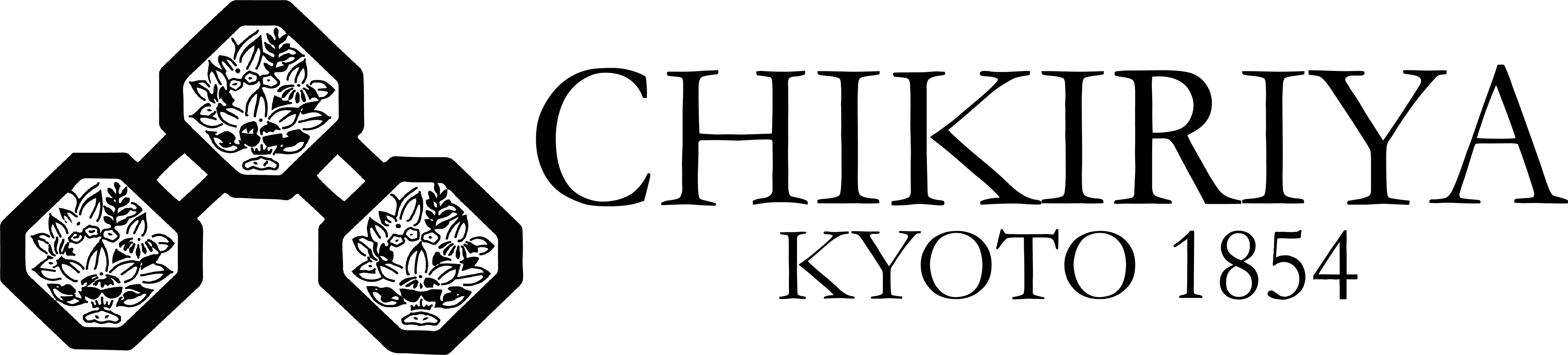お茶について

世の中には昆布茶やどくだみ茶など、さまざまなお茶がありますが、本来「茶」と呼ばれるのは、ツバキ科ツバキ属の常緑樹 Camellia sinensis(カメリア・シネンシス)、いわゆるチャノキからつくられたものを指します。茶は大きく、不発酵茶(緑茶)、半発酵茶(烏龍茶)、発酵茶(紅茶)の三つに分類されます。 不発酵茶は、摘んだ茶葉をすぐに蒸したり炒ったりして酸化酵素の働きを止めてつくられるも...
もっと見る
今週のトピックに入る前に、まずは1912年に作られた日本の古い童謡に少し耳を傾けてみましょう。今でも全国の小学校で親しまれているこの歌は、「夏も近づく八十八夜」という一節で始まります。歌詞こそ素朴ですが、その背景には驚くほど深い意味が込められています。 八十八夜とは何ですか? 「八十八夜」とは、かつて日本人の生活リズムを形作っていた旧暦における特別な日です。旧暦は中国の暦と同様に、季節の移ろ...
もっと見る
日本茶の日(10月31日)の由来を探ろう。日本へ緑茶をもたらした僧侶・栄西を称えるこの日。茶が調和と健康、そして心の静けさの象徴となった経緯を学ぶ。
もっと見る
日本からアフリカ大陸の南端、南アフリカのケープタウンまで旅をしましょう。ここは、世界で唯一のルイボス(Aspalathus linearis)の自生地です。 ルイボスは、ケープタウンの北約250キロに位置するセダーバーグ地域原産のマメ科の低木です。この地域の特有の環境条件が、ルイボスの成長に最適な唯一の生息地となっています。標高450メートル以上のセダーバーグ山脈は、冬季(5月~8月)で0...
もっと見る
お茶に含まれる栄養成分 お茶の成分がお湯に溶けるのは全体の約20%~30%。成分の多くは茶殻に残っています。茶殻まで食べることで、お茶の栄養素を丸ごと摂ることができます。※食べる場合は、一番茶(100g 1,000円以上の煎茶)のような柔らかい葉がおすすめです。(ちきりや商品:宇治本玉露、神泉、新茶各種)※画像をクリックしていただくと、大きく表示されます。 茶殻・茶葉の活用<料理編> 茶殻...
もっと見る
ビタミンと聞くと、棚に並んだ錠剤やサプリメントを想像しがちです。しかし実際には、これらの小さな化合物は、私たちが毎日楽しむ食べ物や飲み物に常に含まれてきました。ビタミンは、体の中で舞台裏で働くスタッフのような存在です。静かにすべてが正常に機能するよう支えています。脚光を浴びることはありませんが、これらがなければ、体の活動は成り立ちません。必須ビタミンは全部で13種類あり、以下の2つのグループ...
もっと見る
たんぱく質は、体内の細胞を生成するために不可欠な栄養素(英語でプロテインといいます)で、エネルギー源としてはたらくほか、ホルモンや酵素類など生理機能を調整するという役割があります。たんぱく質は体内でアミノ酸に分解されますが、体内でつくることができるものと、できないものに分けられます。体内でつくられないものは、食品から摂取する必要があります。体内でつくられないもの(必須アミノ酸): ...
もっと見る