
第88夜の帰還 - カップに宿る季節の物語
今週のトピックに入る前に、まずは1912年に作られた日本の古い童謡に少し耳を傾けてみましょう。今でも全国の小学校で親しまれているこの歌は、「夏も近づく八十八夜」という一節で始まります。歌詞こそ素朴ですが、その背景には驚くほど深い意味が込められています。
八十八夜とは何ですか?
「八十八夜」とは、かつて日本人の生活リズムを形作っていた旧暦における特別な日です。旧暦は中国の暦と同様に、季節の移ろいを細やかに捉えながら、長らく日々の暮らしを支えてきました。現代ではグレゴリオ暦が使われていますが、季節を数えるという感覚は、今も文化や慣習の中にしっかりと残っています。

立春は通常2月3日か4日。その日から数えて88日目の夜が、5月2日(閏年は5月1日)に当たります。歴史的には、稲の種まきや畑の準備、そして最も重要な初摘み茶の収穫など、農作業が本格的に始まる節目の時期でした。
八十八夜が茶にとって重要な理由
八十八夜はちょうど茶摘みの最盛期と重なるため、新茶の象徴とされてきました。「八十八日に摘んだ茶は長寿をもたらす」という言い伝えもあり、これは民間伝承というより、現代の科学的知見にも通じるものがあります。

一番茶には、茶の主要成分であるカテキン、カフェイン、テアニンといった成分が最も豊富に含まれています。これらが緑茶の抗酸化作用、ほどよい苦味、爽快感、そして自然なリラックス効果を形作っています。
研究もこれを裏付けています。
分析によれば、これらの有益な成分は八十八夜の頃にピークを迎え、その後徐々に減少していきます。大阪大学の大規模研究では、緑茶をよく飲む人ほど脳卒中や心筋梗塞後の死亡リスクが低いという結果も示されています。
つまり、古くからの知恵には想像以上の根拠があったということです。
秋に訪れる、もう一つの「八十八夜」
ここから物語は季節を変えます

秋分の前後、日本の気温や土壌温度は不思議と5月上旬とよく似た状態になります。茶農家は昔から、この時期に芽吹く秋の茶葉が、八十八夜とほぼ同じ条件で育つことに気づいていました。
この秋に育つ茶葉は「戻り八十八夜」と呼ばれ、春の初摘み茶の豊かさや調和、生命力を宿すとされる特別な収穫です。
二つの季節をつなぐ一杯

当店の「戻り八十八夜」は、この季節ならではの茶葉を贅沢に使い、丁寧に仕立てた限定茶です。春の新茶のような爽やかさに、秋ならではのやわらかな深みが重なり、清々しさと落ち着きが同居する味わいです。
日差しが穏やかになり、夕暮れが早まるこの季節。二つの季節が出会う一瞬を、一杯の中でじっくり楽しんでいただけます。
この秋限定の茶葉は数量も限られておりますので、ぜひお早めにお試しください。
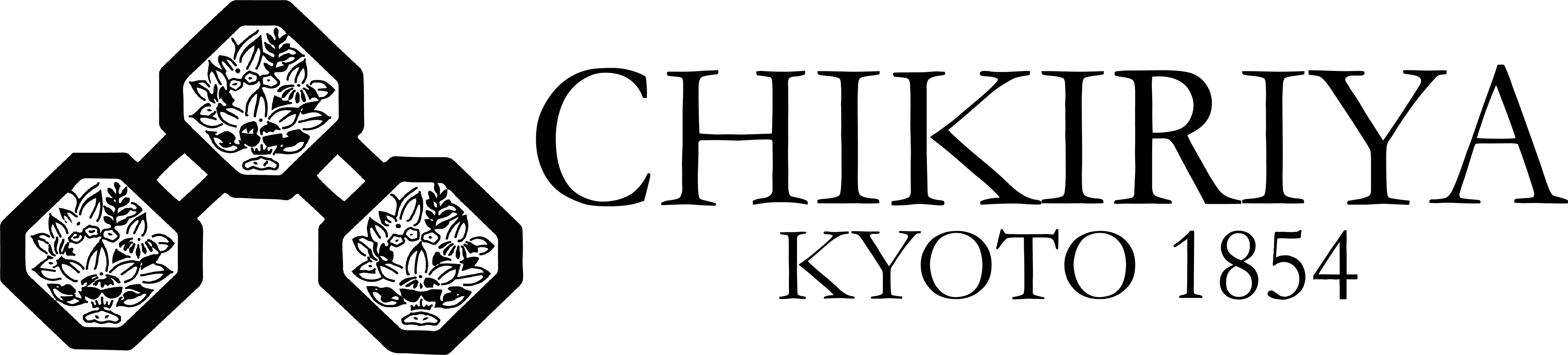



コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。